昭和何年何月何日、僕は生まれて初めての失恋をした。
そう、相手はカツオ。
カツオは僕の初恋の人。それはカツオも同じだと僕は思っていた。
それなのに、カオリという女が背後にいたとは僕にとって青天の霹靂。
嗚呼、無常。
「堀川くん、傘ないのかい?」
そこから僕の初恋は始まった。まさに一目惚れ。男の子同士の相合い傘。
手を繋ぎたかったが、その時はやめておいた。
だって急に手を出したらカツオだって驚くだろう。だから僕は徐々に距離を縮めていくことに決めた。
まず、何をすれば良いのかわからず、僕が一晩中悩んだ末に考えついたことがカツオ身辺のリサーチ。
ワカメに近づくことを決意した。
翌朝、僕はワカメに声をかける。
「おはよう、ワカメちゃん」
「おはよう、堀川くん」
ナイスな一手。
「僕も野球が好きなんだけど、確かお兄さんも野球が好きなんだよね?」
「そうよ。でも、それがどうしたの?」
「お兄さんに近づ…、教えてもらいたくて。今度の日曜日、お兄さん空いてない?」
「うーん、また訊いてみるわ」
ワカメの言葉に僕は歓喜した。これが第一歩目であると。
そして翌朝、僕は朗報を受けることになる。
「お兄ちゃん、空いてるって!」
僕は内心笑った。
「計画通り」
そして日曜日、僕は磯野家に行きカツオを待つ。カツオ姉は僕に警戒心を寄せることなく、僕にいろんな話をした。カツオの幼き頃の話を聞けた時は、それはもう全身が熱くなるような好奇心に駆られて、僕はカツオ姉とカツオについて語らいあった。
そんな時だった。
「ああ、君が堀川くん」
僕の世界に光が舞い降りた。
カツオがにっこり微笑んだ。
「遅くなってごめんな、野球やろうぜ」
「はい!」
こんなにもときめきを感じたのは生まれて初めてのことだった。まさにこれは恋。僕はそう確信した。
公園に着いた僕たち。
カツオはやる気満々だが、僕は野球のルールも知らなければ、野球自体したことがない。
そこで閃く。
手取り足取り教えてもらえたら良いではないか。
「僕、野球をしたことがないんです」
「え?」
「だから教えてください」
カツオは少し困った顔をしていたが、すぐに笑って「分かったよ」と言う。
まず、キャッチボールから。カツオは勉強嫌いということはカツオ姉から聞いていたが、野球面には長けていた。カツオが眩しく見える。
これぞ、僕が望んでいた恋人。
徐々に僕もキャッチボールに慣れてきて、カツオから上達を褒められる。まさに有頂天だった。
次にバットの振り方について教えてもらうことになる。
そこで僕はさらに閃いた。わからないフリをしていれば、カツオが手取り足取り教えてくれるだろうと。その予感は大当たり。
なんとカツオが僕の背後に周り、背後からバットの持ち方を教えてくれる。
ボディフィット。
おそらく僕の血圧は最高値に達しているのではなかろうか。全身がバクバクして、カツオの吐息すらも愛おしく感じた。
そんな時だった。
「あら、磯野くん」
見慣れない女が現れた。
「カオリちゃん!」
カツオの声が妙に高くなる。
カオリ?
僕の体から離れたカツオは、カオリという女の方に歩み始めた。
「何やってるの?」
「見ての通り、野球を教えてるんだ」
僕は見逃さなかった。カツオの頬が紅潮していることに。
嘘だ嘘だ嘘だ、そんな言葉しか頭をよぎらない。カツオ姉はカツオにガールフレンドがいるとは言ってなかったではないか。でも、カツオの目はまさに恋する男の目をしている。
楽しい1日になるはずだった。僕はもっとカツオを知って、好きになるはずだったのに。尊敬と愛情が僕の中で一変した。
「僕、帰りますね」
笑って踵を返したが、腹の中は穏やかではなかった。
帰宅した母親が僕の異変に気づく。
「あら、眉間にシワを寄せてどうしたの?」
「なんでもないよ」
部屋に入り僕はカツオの写真を眺めていた。キラキラ輝くその笑顔に隠されたカオリという女への恋心。
気付けば僕は大粒の涙をこぼしていた。涙を拭いても拭いても止まらない。
これが恋なのか。
そうだとすれば、恋とはなんて残酷なものなのだろう。こんなにも僕の胸を切り裂いて、押しつぶされそうになりながらも生きていかねばならないなんて。
でも、僕は挫けなかった。
カオリよりも良いところがあると証明したかったんだ。
涙を拭いて、すぐさま磯野家に電話。すぐにワカメが出たが、僕はカツオに変わるようにお願いすれば、ワカメは二つ返事で変わってくれた。
「やぁ」
カツオの声が妙に優しく感じた。
「お兄さん」
「なんだい?」
ここから先は、カツオも想定外の発言だったに違いない。
「僕とお兄さんは赤い糸で結ばれています。僕たちの仲は永遠です」
ついに言ってしまった。同時にカツオをこの手に入れたという喜びを感じる。
こんなロマンチックなことを言われたら。誰だって落ちるだろうと僕は踏んでいた。しかし現実は甘くなかった。
「赤い糸も白い糸も関係ないんだよ!」
どうやら、僕のこのロマン溢れた言葉はカツオにうまく伝わらなかったらしい。
僕は落胆した。追い討ちをかけるようにカツオが言う。
「僕はカオリちゃんが好きなんだ。それに僕は同性愛者ではない」
目の前が黒く染まる。
なんて言えばいい?
それだけが脳裏を過って、僕はまた涙を流した。
嗚咽しそうになったが理性を保ち、「分かりました、では」と言って電話を切った。
僕の初めての恋は実らず、踏み躙られたようなもの。
その晩、僕は夢をみた。
カツオと僕が二人きりの甘い生活をする夢を。
これが僕の初恋の顛末だ。
だが、僕はカツオを想い続ける。いつかこの想いが届くことを夢に見ているのだから。
痛みを知った人間は強くなるというが、僕は十分すぎる痛みを知った。だから僕は一つ強くなったはずだ。今回は失恋に終わったものの、僕の気持ちは変わらない。
永遠に。
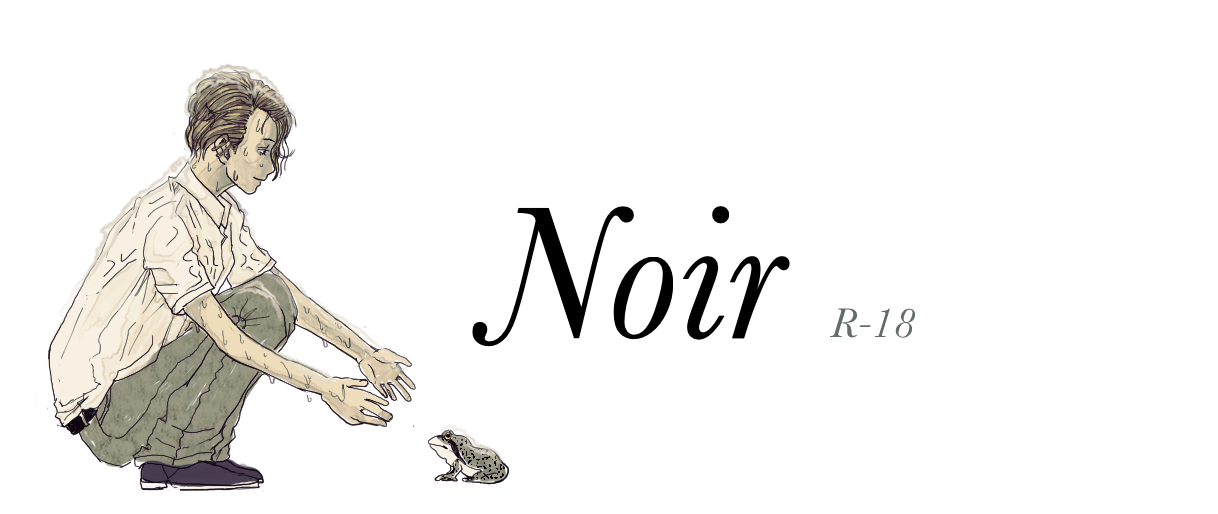



コメント